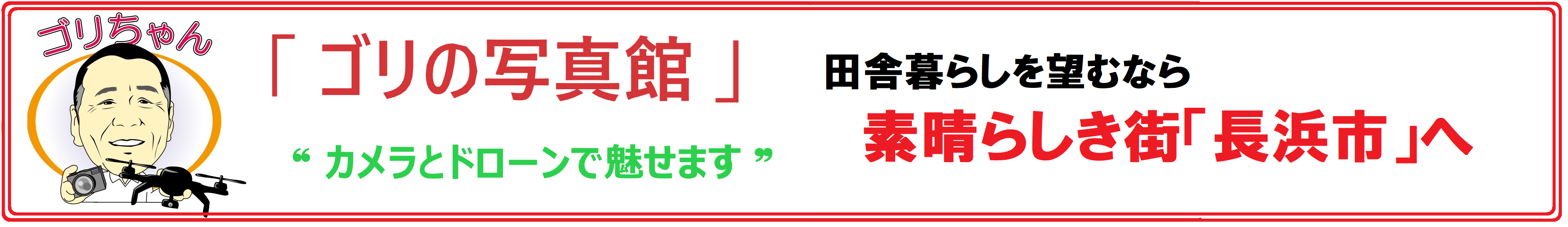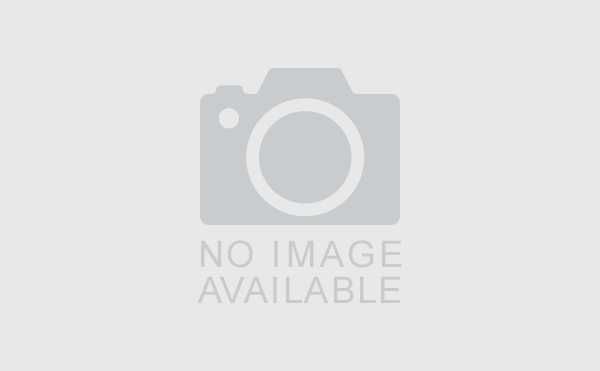琵琶湖にそそぐ大河「姉川」の河口付近の風景七変化は自然が作り出した造形美です! (ドローン空撮・4k動画)

琵琶湖にそそぐ「姉川」は、源を伊吹山地に発し米原市から長浜市を流れ、長浜市南浜地先でびわ湖に注ぐ延長39kmの河川です。
その途中で「草野川」と「高時川」と合流し、1本の大河「姉川」となるため延長の割には幅広い河川です。
滋賀県のほとんどの河川は琵琶湖にそそぎ全部で460本もある中で、この姉川は群を抜いて大きな川です。

昔話の一つとして、「姉川と妹川」の伝説があります。大昔、川がなかった谷に大きな池が出来、大雨で氾濫しそうになった時、そこに住んでいた姉妹は、山が崩れるのを防ぐため、たまった池の水を抜こうと池に飛び込んだそうです。
そして、二人の姫はきれいな龍に姿を変え、二人の龍は、池から吐き出された水と一緒に谷筋に沿って一気に駆け下りて行きました。
そのお陰で、池の水は勢いよく流れだし、山々は落ち着きを取り戻し、この水が流れたところはそのまま川となったとのこと。
この川のおかげで田んぼも作れるようになり、村人たちはこの二つの川を「姉川」と「妹川」と名付けました。その「姉川」は今の姉川、「妹川」は今の高時川という昔話が伝わっています。

琵琶湖は約440万年前に形成された古代湖であり、40~100万年ほど前に現在の位置に移動してきました。
また、琵琶湖は、古くは淡海・鳰におの海などとも呼ばれ、「Mother Lake」の愛称や「近畿の水瓶」の別称で呼ばれることもあり、滋賀県民にとっては愛着のある湖なのです。
そして、その琵琶湖に流れ込む姉川の流れの途中には、戦国時代の戦いの舞台となった古戦場も存在し、姉川の流れは悠久の歴史を物語っています。
この動画を見てお分かりのように、遠くに見える霊峰「伊吹山」をはじめとする伊吹山系の山並みから流れ出る水を集めた姉川は、流水が絶えることなく流れ続けてきました。
時には、大雨により清流が濁流へと変わり、下流に土砂を運び続け、河口付近は長い年月を経て大河が造り上げた見事な扇状地を造り出してくれました。
そして、そこに人が住みつき集落に発展し、肥沃な土地で糧を得ながら、今見るような集落へと変貌を遂げています。

今回の投稿した映像は、姉川河口風景の七変化です。この映像ら見て取れる琵琶湖と姉川の接点付近にできる中州を見るだけでも面白いものがあります。

川の流れは山々の土砂を琵琶湖まで運び、時間を経て作り上げた地形が中州です。その中洲付近には魚やサギなどの野鳥もたむろし、動植物の楽園となっています。
この扇状地を分けて流れ込む姉川と、青き琵琶湖とのマッチング風景は、自然が作り上げた見事な造形美ではありませんか。