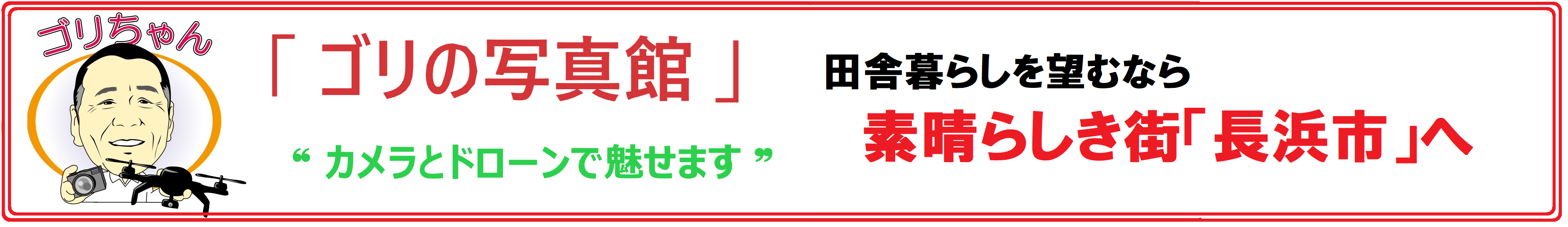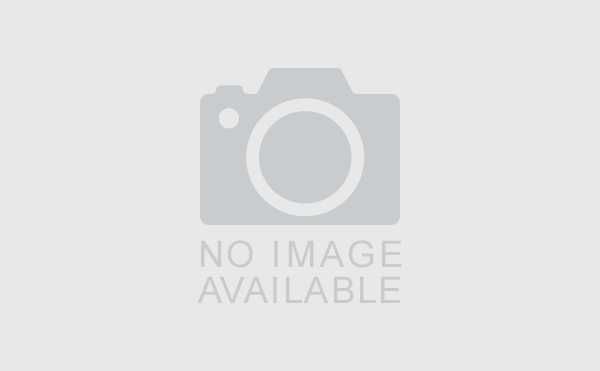江戸末期の農村土木技術の粋を集めた構造物「西野水道」の河口景色(ドローン絶景空撮・4k動画)

昔、現在の西野集落(長浜市高月町西野)は、山・川・地形の関係で大雨・洪水による被害を頻繁に受けていました。
そのため、村を守るために、住民主体で「山をくり抜いて放水路を作り、余呉川から琵琶湖へ直に排水を通そう」という構想が生まれ、長い歳月をかけて出来上がったのが西野水道です。
今回は、琵琶湖に注ぐ西野水道河口付近の素晴らしき景観を、ドローンで空撮しましたので投稿します。今まで何回も投稿していますが、新機種Mavic4proでは初めての撮影となります。
工事着手は天保11年(1840年)頃で、貫通したのは1845年(弘化2年)の記録が残っています。
長さは約220〜250mで幅は約1.5m前後、高さは約2m前後の素掘りのトンネルで、硬い花崗岩質の山を金づちとノミで少しずつ削るため、非常に危険で時間のかかる作業でした。
明かり取りのために竪穴をいくつも掘り、内部の換気や土砂の排出にも使われました。村人総出で作業し、完成時には「天に抜けた」と歓声が上がったと伝わっています。

江戸末期の農村土木技術の粋を集めた構造物で、当時としては全国でも珍しい排水用トンネルでした。後の治水技術発展にも影響を与えたとされ、現在は滋賀県指定史跡(1979年指定)として保護されています。
今では、排水トンネルとしては使用されておらず、トンネル内部を歩いて探検できるというユニークな体験ができる遺跡スポットになっています。予約をすれば見学時はヘルメット・長靴・懐中電灯などの装備が貸し出してもらえます。

その後、素掘りの小さなトンネルでは洪水被害を軽減することが出来ず、時代・技術の進展と共により大きな放水能力を持つトンネルが2代目・3代目の放水路(トンネル)として増設されました。
現在の状態は、前述したように3本のトンネルがあり、北側から順に素掘りのトンネル、昭和の時代に増設された第二トンネル、そして、現在、余呉川の水を琵琶湖に流している第三トンネルがあります。

遺跡となっている素掘りのトンネルを歩くのは、真っ暗でかなり勇気がいります。団体で通り抜けする場合は何とかなるのですが、一人や二人では怖くて行けません。
そこで、便利なのが第二トンネルです。かなり大きめのコンクリートで造られたトンネルで、今は、歩行者専用の通路となっており、琵琶湖河口まで安心して歩いていけるようになっています。

ここの史跡探検は、先人の苦労の軌跡を実感するだけでなく、出口付近から見る琵琶湖を望む景色も魅力のひとつです。投稿した空撮映像を見て頂ければお分かりのように、トンネルを抜けた先に広がる湖の風景が、探検の先のご褒美のようです。
第二トンネルを使えは、老若男女問わず手軽に味わう事が出来ます。ぜひ行ってみてください。