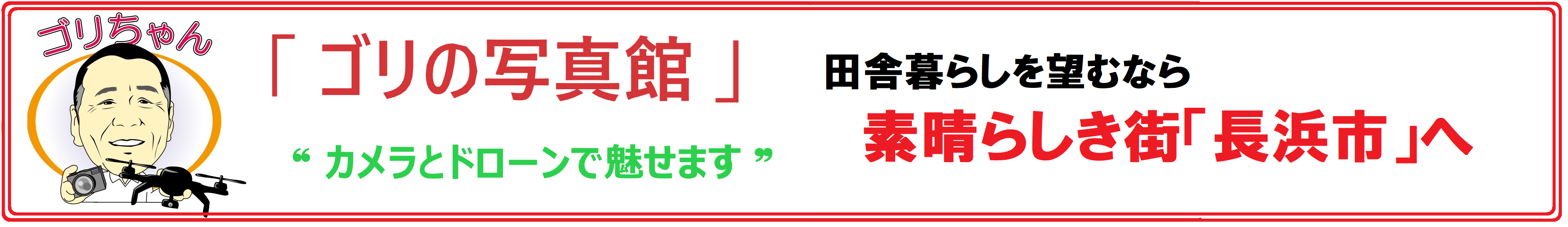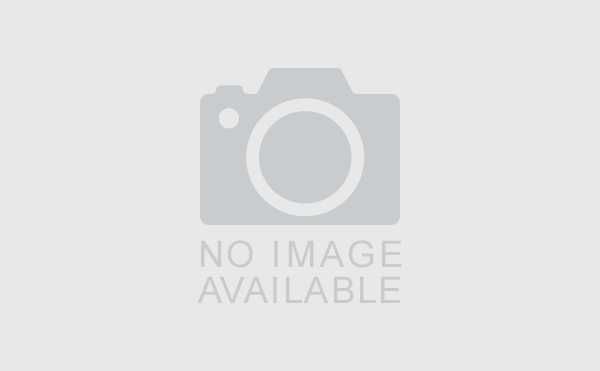長野県の寝覚ノ床は壮大で独特な岩の造形の自然景勝地で、浦島太郎伝説がある観光地(ドローン空撮・4k動画)

長野や諏訪湖方面からの自宅への帰りに、高速料金節約のため一般道で何回か利用した中山道沿いの国道19号沿いにある場所に、今回はターゲットを当ててみました。
中山道は江戸と京都を内陸経路で結んだ街道で、現在でも沿線沿いには馬籠宿(まごめ)や妻籠宿(つまご)など江戸時代の風情を残す街並みが残っている有名な観光地もあります。
そんな風情のある木曽川沿いを走る国道19号で、山の中をくねくねと曲がる道中に、違和感のある浦島太郎の看板が立っている場所があります。
そこは、寝覚ノ床(ねざめのとこ)と言われる景勝地です。今回は、ここをドローンで空撮しましたので紹介します。
寝覚ノ床は長野県木曽郡上松町にある壮大で独特な岩の造形が特徴の景勝地で、浦島太郎伝説がある観光地でもあります。
木曽川の激流が花崗岩を削って形成した、約1.5kmにわたる奇岩群が見どころで、奇岩や渓谷の美しさで知られており、国の名勝にも指定されています 。

2020年には中央アルプス国定公園の一部としても登録され、自然美と歴史が融合したスポットとして観光客に親しまれています 。
また、巨大な白い花崗岩が川沿いに連なる不思議な景観は、「木曽八景」のひとつにも数えられています。
更には、水量の変化によって岩肌が露出するため、天候や季節によって異なる表情を見る事が出来るそうです。

浦島太郎は海辺のイメージが強いですが、なぜ山の中に名前が残っているのか疑問があり、寝覚ノ床という名の由来と伝説について調べてみました。
浦島太郎が竜宮城から帰ってきて現実世界に戻った後、時の流れの早さに絶望し、各地を放浪しました。そしてこの地、木曽の地に辿り着き、木曽川のほとりでしばらくの間世捨て人のように暮らしていたと言われています。
太郎はそこで「目を覚ました」ように現実を悟り、この岩場に座して物思いにふけったこのことから「寝覚ノ床」という名前がついたとされています。

この伝説に基づいて、寝覚ノ床の岩場の中には「浦島堂」と呼ばれる小さなお堂があります。これは、浦島太郎を祀った建物であり、地元の人々や観光客が訪れるスポットでもあります。
もちろん、浦島太郎の話は日本の昔話・伝説にすぎないため、史実としての裏付けはありません。
自然の荘厳さや時間の流れを感じさせる景観がこの伝説と結びつき、人々の想像をかきたて、今に残っているのだと思います。