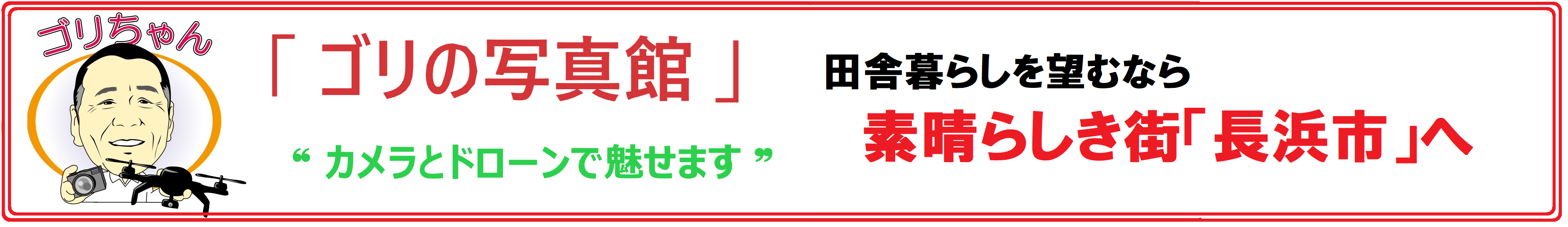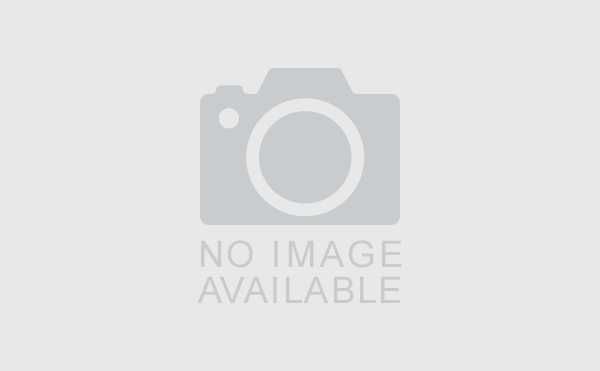「日本の最後の清流」と称される四万十川に架かる沈下橋は独特な橋で、日本の原風景とも言える美しい景観です! (ドローン空撮・4k動画)

昨年の春にドローン県外遠征で訪れた四国の高知県を流れる四万十川に架かる有名な橋の映像を、今回は蔵出しします。
高知県を流れる四万十川は「日本の最後の清流」と称される川です。その川に架かる沈下橋は独特な橋で、日本の原風景とも言える美しい景観と共に、多くの観光客に親しまれています。
四万十川の沈下橋は現在も47本の沈下橋が残っていて、増水時に川の水に沈むことを前提に設計された橋です。
欄干や手すりがなく、橋自体が低く作られており、洪水や大雨の際には水没して流れの抵抗を受けず、破損を防ぐようになっています。

今回撮影した橋は、高知県高岡郡四万十町に位置する「一斗俵沈下橋」です。1935年に建設された、四万十川に現存する最古の沈下橋です。
その歴史的価値から、2000年に国の登録有形文化財に指定されました。現在は車両通行が禁止されておりますが徒歩での通行が可能です。

大きな川に橋を架けるのは大変なことです。橋を架けるのはトンネルを掘るのと同様に多額の費用が必要だからです。
川幅の広い四万十川に橋を架けることは、その難点を克服する必要があり、生み出されたのが沈下橋でした。
そして、交通が不便だった時代、沈下橋が地域の人々の生活道路として重宝されてきました。
橋の構造は地域の大工が施工し、地元の技術が集結して造られています。現在では文化的価値が評価され、保存・修繕の取り組みも行われて現在に至っています。

辺鄙な場所で収入減に乏しいからこのような橋が造られたという概念があれば、払しょくする必要があります。
自然の力を受け入れ、逆らわないという「共生」の知恵が形になっているのです。土木技術の観点から見ても、無駄がなく、目的にかなった美しさがあります。
また考え方を変えると、このような簡易な橋は理にかなった橋なのです。
一般的な橋を設置するには多額の費用が掛かり、昨今、対応年数も経過し老朽化が進んでいる橋がたくさんある中で、維持管理経費の問題や付け替えの問題などが話題となっています。そんな中、無駄のない沈下橋の考え方は、これからの橋の架け替えに参考にすべき点があるような気がします。

今回のドローン県外遠征の中で、初めて訪れた四国にある日本の最後の清流と呼ばれている四万十川にて、有名な沈下橋をつぶさに見る事が出来ました。
四万十川に多く見られる沈下橋は、地元の人々にとって生活道路の一部となっています。農作業の道具や自転車、軽トラで渡る人々の姿が見られ、現代的な交通インフラとは異なる素朴で温かい生活の風景がそこにはありました。